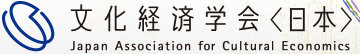福島県浜通り地域における経済産業省のアート施策について
経済産業省福島芸術文化推進室 志村 環太
◆経済産業省福島芸術文化推進室とは
経済産業省(以下、経産省)は2023年6月「福島芸術文化推進室」を設立した。当室は、東京電力福島第一原子力発電所事故によって避難指示等の対象となった福島県の浜通り地域を中心とする12の市町村において、「芸術・文化を通じた魅力あるまちづくり」を推進することを目的とした組織であり、室員は経産省に籍を置く若手の有志職員によって構成されている。
本稿は、室員である筆者の目線から、福島の原子力被災地における芸術・文化によるまちづくりの取組の一部を紹介するものであり、一部に個人的な見解を含むことをご了承いただきたい。
福島や浜通りと聞いて、どのような現状をイメージされるだろうか。東日本大震災やそれに伴って引き起こされた原子力発電所事故のイメージを持たれている方々が多いのであろうとは推察しているが2011年3月の印象、そして自分の地域とは異なる場所で止まっている、つまり時間軸的にも物理的にも遠く離れた場所、どこか自分とは関係のない場所というのが正直なところではないか。当室は、その印象を覆し、多くの人と福島や浜通りとの繋がりを作っていくための取組を実施している。
◆ハマカルとハマコネについて
当室は取組の一部として、「映像芸術文化支援事業」と「映像・芸術文化を通じた関係人口創出事業」の、2つの補助事業を実施している。前者は「ハマカルアートプロジェクト」という名称で、所謂アーティスト・イン・レジデンスに着想を得た事業で、浜通りを中心とする12市町村で実施する滞在型のアートプロジェクトを支援している。後者は「ハマコネ」という名称で、アートと商品開発やイベント実施などを掛け合わせたプロジェクトを支援している。
両事業では、多数のプロジェクトを採択しているが、それぞれ一事例ずつ紹介する。
ハマカルアートプロジェクトでは2024年度、福島県双葉郡富岡町夜ノ森地区に故郷をもつ秋元菜々美氏と建築集団ガラージュとがタッグを組んだプロジェクトを採択した。夜ノ森地区はもともと福島県を代表する桜の名所で、全長2.2㎞にわたり420本の桜が植えられ多くの観光客で賑わう地域だった。富岡町の中心地域の避難指示は2017年4月1日に解除され、この夜ノ森地区においては、6年後となる2023年4月1日に避難指示が解除された。一方で、富岡町全体の人口は、約2300人程度と原発事故前の約1/8程度であり、夜ノ森地区の人口も大きく減少していることが窺える。
この夜ノ森地区は、地震や原子力災害の影響で、10年以上にわたり帰還がかなわない地域であった。この結果、多くの建物が老朽化し、解体を余儀なくされている。ガラージュはそこで、主に町の変遷についてのリサーチを行った。町役場や国土地理院などの地図を比較し、足を動かし町を見て、住民へのヒアリングを通して夜ノ森地区の歴史を紐解いていく、そんなプロジェクトである。筆者は活動報告会である町歩き企画に参加したが、ガラージュ作成の地図を片手に、夜ノ森地区に精通した住民の案内でまちの変化を確認していくものであった。当室の目的は「芸術・文化を通じた魅力あるまちづくり」であるが、その対象となる「まち」そのものを、住民と共に紐解いていく。そのプロセスやアウトプットはこのまち・この地区における価値として残っていくのではないかと思う。
次に、ハマコネでは「YoiYoi」というお祭りを企画するクラフト日本酒の醸造所haccobaによるプロジェクトを紹介したい。クラフト日本酒とは、日本酒の製法に例えばホップやハーブなどを加え、法的には日本酒に該当しない新しいジャンルの酒のことである。haccobaは南相馬市小高区と浪江町藤橋に醸造所を有している。どちらの地域も先述の夜ノ森地区と同じく、避難指示対象となった地域である。そのような地域で酒蔵を営むhaccobaが当該地域と外の地域とを繋げるために始めたイベントが美食と音楽の新体験フェス「YoiYoi」であり、1年目は浪江で開催され好評に終わった後、2年目が南相馬で開催された。参加者はhaccobaのクラフト日本酒を自由に飲むことができるだけでなく、隣接地域の他の酒蔵のお酒や、ジビエや旬の野菜を使った野性味あふれる料理を楽しむことができる。それだけではなく、GotchやChelmico、篠田ミル、小林うてなといった人気アーティストによって音楽が奏でられる極上の空間であった。100人規模とはいえ、音楽フェスを、イベント会社を挟むことなく1つの酒蔵が地域の方と協力し、実現に漕ぎつけたことは、感動的でさえあった。次回も開催されるのであれば、学会の皆様にも是非足を運んでいただきたい。
本稿では、頭角を現しつつあるアーティストたちと地域との共同によって、まちを深堀っていく取組と後者の実力のあるアーティストと地域とが協働し、まちに賑わいをもたらす取組といった対象的な取組を紹介したが、この幅の広さこそが、2つの性格の異なるプロジェクトを同時に実施していることの醍醐味であると思う。12市町村は、他の地域に比べればとにかく人が少ない。これは紛れもない事実である。しかし、こうした取組を実施できるような魅力ある人たちが多く集まる地域ともなっている。魅力あるまちづくりを目指す上では、そうした人たちが集まること、そして、連鎖的に人の魅力が花開くような場所となる事が必要ではないか。
◆アートとまちづくりの接点
「役人が、自分たちではどうすることもできないから、アーティストやアートを利用するだけ。」室が立ち上がって間もない頃、あるトークイベントに登壇した筆者に寄せられたご意見だ。国が「アートを用いて」施策を打つことにある種の違和感や嫌悪感を抱く方も当然いらっしゃる。このような意見が出てくる背景には、アートという、不確定性や定量的に観測できない力を持つものと、まちづくりという目的的な行いとがイコールで繋がらないのにも関わらず、アートを目的的な行いに矮小化しようとしているように見えるからではないかと思う。我々の活動に、そのような意図はない。
一方で、役人である筆者からしてもアートは直接的にはまちづくりに繋がるものではないと考える。アートプロジェクトを実施したことで、即ち住民が増え、まちの税収が増え、多方面で潤っていくというのは極めて限られた例でしかない。
では、なぜ国が、しかも経済・産業を冠する官庁がアートに関わるのか。その理由は、アートには鑑賞者に何らかの影響を与え、鑑賞者を媒介に世界に影響を与えていく力が確実に備わっているからであると考えている。その力は、心理的影響に留まらず、体験を通じて行動に影響が現れる。(これが体系的に整理された理論・研究について、もしここまでお読みになった方でご存じの方がいれば、ご教示いただけると幸いである。)当プロジェクトを通じて、そういった一連の効果を注視し、分析し、論理立てていくことができれば、福島のみならず、幅広い応用を効かせることができるであろう。
◆おわりに
ハマカルアートプロジェクト及びハマコネは2025年度も活動を始めている。アートという取組、メディア、コミュニケーションを通じて、福島を取り巻く社会問題等と関わり合いながら、新たな表現、新たな価値観、新たな文化、歴史の継続を生み出す仲間が、本稿をきっかけに増えていくことを切に願っている。